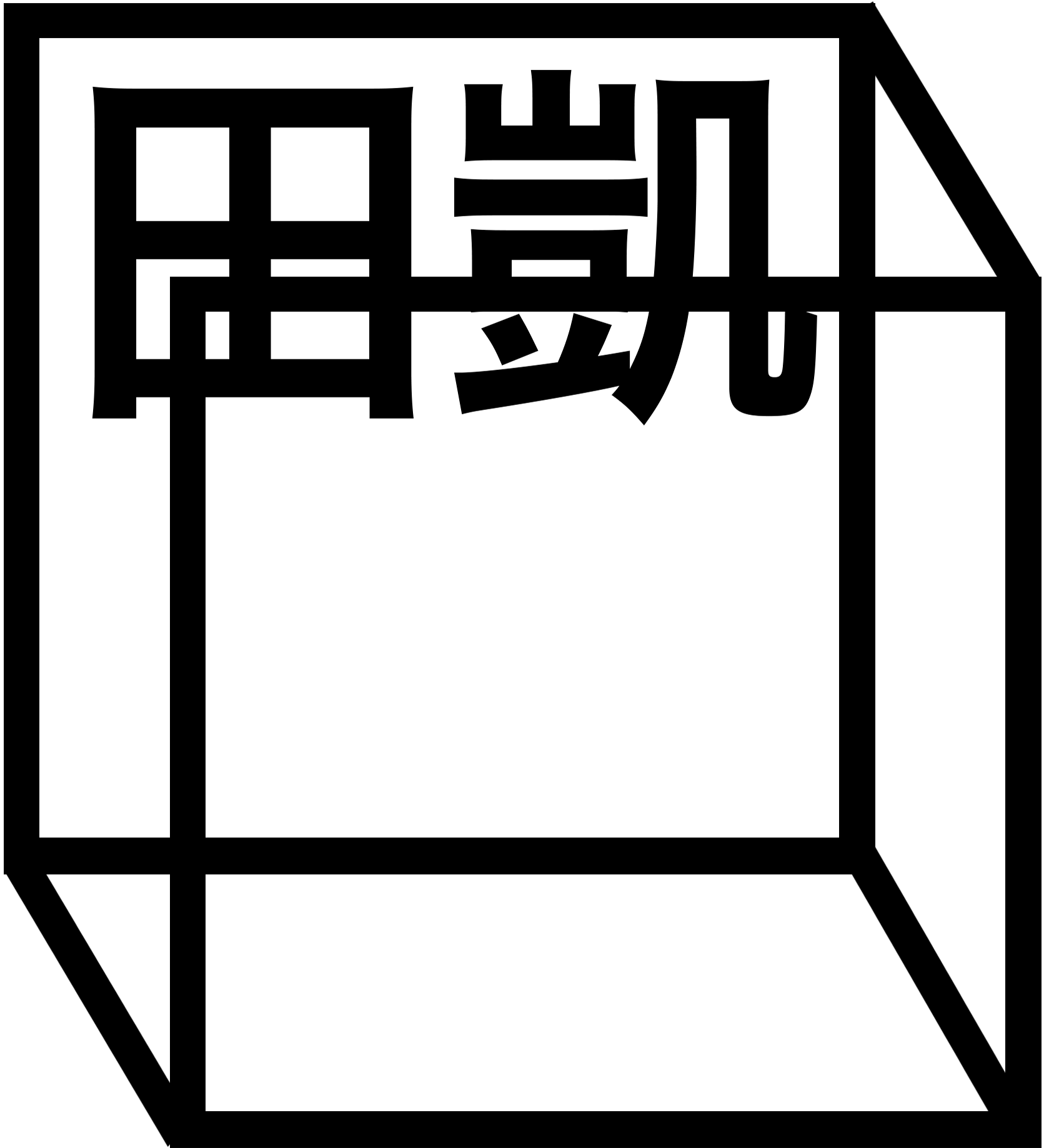[Correspondence With The Past]
This work is composed around six diary entries.The author of these diaries was an intellectual—educated in the city, which was still rare at the time, and even completing university—yet he chose to respond to the ideological fervor of his era. With a sense of purpose and personal conviction, he accepted an assignment to a remote oil town. The place he was sent to stood at the very "front line" where the feverish enthusiasm and contradictions of national construction collided.He spent many years there as a laborer and eventually retired.But his life did not conclude there.After retirement, he once again took up the pen, pouring his former passion and the emotions that welled up in each moment onto the page with striking density and clarity.His writing captures not only the atmosphere of the worksite, but the faces, voices, smoke, heat, even the tone and cadence of conversations.Reading the diaries, one feels as if traveling through a time machine—moving back and forth between past and present.But I did not want to simply “read” these diaries.I wanted to respond.So I took my camera and recorded the present-day landscape of the oil town, using negatives reversed and reloaded—an attempt to offer a visual reply to the written words.The courtyards that once echoed with voices and laughter, beneath skies scorched by pillars of fire, are now littered only with rusted tin roofs, shattered glass, and weeds swaying in the wind.That contrast pierced me deeply.The written words burn with fire.But the place from which they emerged now lies in frozen time.It felt as though the voices that once called out and the landscape that now refuses to answer coexist in silence—side by side, never meeting.The reversed negatives glow red.And in that color, what emerges is a fissure—a veil—between the passion and decay of the pioneers, between speech and silence, between the former brilliance and present emptiness.But this is not a denial of the past.Rather, I believe it is a quiet yet determined response to a question we all face today:How do we look at the past? How do we confront memory?
この作品は、6通の日記をもとに構成されている。その日記の筆者は、若き日に都市で教育を受け、当時ではめずらしい大学まで行かれてインテリとして育ちながらも、時代のイデオロギーに呼応し、自らの意志と使命感を携えて、石油の町へと赴任した人物である。彼が派遣されたその地は、国家建設の熱狂と矛盾とが交錯する、まさに「最前線」であった。彼はその地で労働者としての年月を積み重ね、やがてリタイアを迎えるが、そこで人生の筆を置くことはなかった。退職後、彼は再びペンを手に取り、かつての情熱と、その時々にこみ上げた感情を、奔流のような密度で記していく。日記には、現場の息遣いや、顔、声、煙、熱、語気までもが生き生きと刻まれており、それはまるで過去と現在を行き来するタイムマシンのように機能している。私は、その日記をただ「読む」のではなく、応答するという行為によって向き合いたいと思った。そこで私は、現在の石油の町を、ネガを裏返して装填して撮影した。日記の言葉に対して視覚的な応答を試みた。かつて火柱が空を焦がし、人々の声と笑いが中庭に響いていたその場所には、今では朽ちたトタンの屋根、割れた窓ガラス、そして風に揺れる雑草だけが残っている。そのコントラストは、私の胸を鋭く刺した。書かれた言葉は炎のように熱い。だが、それが生まれた場所はいま、凍てついた時間のなかにある。まるで、呼びかける声と、それに応じることのない風景が、すれ違いながらも並列して存在しているようだった。反転された写真は赤く染まり、そこにはかつての開拓者たちの情熱と荒廃、語りと沈黙、輝きと空虚――それらが交差する裂け目、あるいは「遮蔽物」が浮かび上がってくる。だが、それは過去への否定ではない。むしろこれは、私たちがいま「過去をどう見るか」「記憶とどう向き合うか」という問いに対する、静かな、しかし確かな応答である。
1. 1972年6月4日――それは、私が旧採油第一隊に正式に配属された日だった。
カレンダーを見返すと、その日は日曜日で、夕食後の政治学習会が珍しく開かれなかった。だから敖綿と私は、庭に出てざる碁を打ったのだった。翌日、月曜の全体例会に参加して、私はさっそく度肝を抜かれることになる。
隊長の余維海――四川出身で、背が高く痩せ型、真っ黒に焼けた肌に、大きな目がぎょろりと光る。早口になると、四川訛りがそのまま噴き出す。誰の話だったかはっきり覚えていないが、彼の声はヒスノイズのように響き、大目玉で怒鳴りつけるその様子には本当に震え上がった。あの厳しさは、「五七乾校」で「五一六分子」の摘発をしていた頃や、階級闘争の真っ只中ですら見たことがない。あの時の旧第一隊には自転車が二台しかなく、ボロボロの「紅旗28」は資材部の人間が毎日使っていた。そして新品の「飛鳩28」は、まるで私物のように隊長・余の専用だった。
黄色いビニールテープで巻かれたフレームが美しく、彼の家は採油指揮本部のすぐそばにあったが、平日は我々一般隊員と同じく現場に泊まり、日曜だけ家に戻る。毎週月曜の朝、現場に帰ってくると、剃りたての髭のあとがまだ青く、肌は焼き鉄のようにくすんでいて、その顔つきはさらに威圧感を増していた。あの「飛鳩28」は、ほとんど誰にも貸さなかった。ごくたまに、ベテランの隊員にだけ使わせることもあったが、それ以外は完全に独占していたと言っていい。若い者たちは、彼のあの恐ろしい顔を見ると、うまく理由をつけて逃げ出した。私も若かった。彼がなぜ常に怒っているのか、まったく理解できなかったし、彼に家族がいるのかどうかさえ疑わしく思えた。
そうだ、あの夜に叱責されていたのは楊成剛だった。彼も大柄な男で、叩かれたその場で反論を始めたが、後輩だった彼は大事になる前に引き下がった。楊鳳英姉さんも名指しされていたが、肩を叩かれたかどうかまでは定かではない。
もちろん、旧採油第一隊の歴代の隊長がみな余隊長のような「鬼」だったわけではない。後任の王玉珠は、背は高くなかったが、ややふくよかで、慈眉善目の優しい人柄だった。転任の会で彼女の演説を聞いたときは、本当にほっとしたものだ。「ようやく鬼から解放された」と心の底から思った。
指導委員の王文達も、軍隊からの転属だったからか、演説は筋が通っていて、余隊長ほどのマッチョな厳しさはなかった。長く勤めたのちに、工農課長に転任した。
旧第一隊の初代隊長だった張慎民のことも、よく語り継がれていた。彼は20人を率いて第一採油チームを立ち上げ、現場設営に成功した人物だ。多くの人々が彼を懐かしんでいた。経験豊富なベテランで、ときに険しい顔をすることもあったが、見習いの隊員たちを我が子のように可愛がってくれた。だからこそ、みんなに尊敬されていたのだろう。
その後、岳鳳生も隊長に任命された。彼もややぽっちゃりしていて、見習いに対していつも親切だった。隊長職のあと、調達部門に異動していった。
私の覚えていること、そして知っているのは、これくらいだ。
2
私が彼の家を訪ねたのは、たしか1973年の元日の前日だった。場所は、胡同の北西の角、大寺という町のすぐ近くだった。胡同の路地はくねくねと入り組んでいたけれど、それでも私は迷わず彼の家にたどり着いた記憶がある。ただ、もしあの界隈が再開発されてしまったなら、今はもう別の風景になっているだろう。
彼の母親は、当時まだ五十手前の年齢だったが、細身で元気そうで、現役で働いていた。彼は結婚したばかりで、新居はこぢんまりとしていた。ツインベッドに、三枚扉のクローゼット、酒専用のキャビネット、ソファ――それらすべてが彼の手作りだという。手入れの行き届いた部屋に着くと、兄嫁がちょうど仕事から帰ってきた。
目を引いたのは、新品の「飛鳩28」の自転車だった。ピカピカに磨かれたフレームが眩しいほどに光っていた。ベルの付いた大きなチェーンボックスも、まるで装飾品のようだった。中庭に入る前、入口の外でドアベルが鳴り響くと、チェーンボックスも「チーン、チーン」と軽やかな音を立てた。それは、当時の若者たちが羨望し、憧れ、追い求めたファッションそのものの象徴だった。
私はもともとマトンの匂いが苦手だったが、その夜、李明の家で出された夕食の美味しさで、すっかり苦手意識が吹き飛んでしまった。
翌朝――元旦の早朝、李明の兄が私を「大福来」へと連れていってくれた。天津名物のガーバー菜と揚げパンを頬張りながら、私は李明から「大福来」の由緒について話を聞いた。
思えば1972年の春節前、ニクソンの訪中が決まり、私のような者は北京から粛清された。それで最初は河北省清県にいる従兄弟のもとへ向かい、天津を経由して、5月末には油田に正式に籍を置いた。その間に二度、天津東駅近くに滞在した。
今回は、李明がガイド役を買って出てくれて、和平路の繁華街をじっくりと案内してくれた。彼は、ある建物の壁に掲げられた「勧業場」の三文字を指さしながら、これは華士魁の書によるものだと教えてくれた。華士魁は、解放前には「一字千金」の異名をとった名高い書家だった。
私はかねてより「北京の四合院、天津の西洋館」という言葉を聞いていたが、その日、本物の西洋館の外観を初めて目の当たりにした。
北京と天津は距離こそ近いものの、その趣はまったく異なる都市である。北京は道幅が広く、街路は直線的で、建物も整然としており、どこか隅々まで管理が行き届いた印象を受ける。一方の天津は、海河が蛇行し、ゆるやかな地形に寄り添うように道路が走っていて、さまざまな様式の小ぶりな建物が建ち並んでいる。どこか異国風の、洗練された雰囲気が漂っていた。
人々の服装にも、その差は顕著だった。北京では、単色の制服が主流で、正統性と厳粛さはあるが、どこか活気に乏しかった。天津の人々は、細部に凝った仕立ての服をまとい、スタイルがあり、当時の北方三地域のなかでも、ファッション面で一歩先を行っているように感じられた。
私の稚拙な描写では、そこに宿っていた空気――物が帯びる「オーラ」のようなものを、どうにも伝えきれないのがもどかしい。自分の文章力を情けなく思う。そしてそれだけでなく、今日この目で北部工業地帯の衰退を見るたび、胸が締めつけられ、言葉が出なくなってしまうのだ。
2.
私が彼の家を訪ねたのは、たしか1973年の元日の前日だった。場所は、胡同の北西の角、大寺という町のすぐ近くだった。胡同の路地はくねくねと入り組んでいたけれど、それでも私は迷わず彼の家にたどり着いた記憶がある。ただ、もしあの界隈が再開発されてしまったなら、今はもう別の風景になっているだろう。
彼の母親は、当時まだ五十手前の年齢だったが、細身で元気そうで、現役で働いていた。彼は結婚したばかりで、新居はこぢんまりとしていた。ツインベッドに、三枚扉のクローゼット、酒専用のキャビネット、ソファ――それらすべてが彼の手作りだという。手入れの行き届いた部屋に着くと、兄嫁がちょうど仕事から帰ってきた。
目を引いたのは、新品の「飛鳩28」の自転車だった。ピカピカに磨かれたフレームが眩しいほどに光っていた。ベルの付いた大きなチェーンボックスも、まるで装飾品のようだった。中庭に入る前、入口の外でドアベルが鳴り響くと、チェーンボックスも「チーン、チーン」と軽やかな音を立てた。それは、当時の若者たちが羨望し、憧れ、追い求めたファッションそのものの象徴だった。
私はもともとマトンの匂いが苦手だったが、その夜、李明の家で出された夕食の美味しさで、すっかり苦手意識が吹き飛んでしまった。
翌朝――元旦の早朝、李明の兄が私を「大福来」へと連れていってくれた。天津名物のガーバー菜と揚げパンを頬張りながら、私は李明から「大福来」の由緒について話を聞いた。
思えば1972年の春節前、ニクソンの訪中が決まり、私のような者は北京から粛清された。それで最初は河北省清県にいる従兄弟のもとへ向かい、天津を経由して、5月末には油田に正式に籍を置いた。その間に二度、天津東駅近くに滞在した。
今回は、李明がガイド役を買って出てくれて、和平路の繁華街をじっくりと案内してくれた。彼は、ある建物の壁に掲げられた「勧業場」の三文字を指さしながら、これは華士魁の書によるものだと教えてくれた。華士魁は、解放前には「一字千金」の異名をとった名高い書家だった。
私はかねてより「北京の四合院、天津の西洋館」という言葉を聞いていたが、その日、本物の西洋館の外観を初めて目の当たりにした。
北京と天津は距離こそ近いものの、その趣はまったく異なる都市である。北京は道幅が広く、街路は直線的で、建物も整然としており、どこか隅々まで管理が行き届いた印象を受ける。一方の天津は、海河が蛇行し、ゆるやかな地形に寄り添うように道路が走っていて、さまざまな様式の小ぶりな建物が建ち並んでいる。どこか異国風の、洗練された雰囲気が漂っていた。
人々の服装にも、その差は顕著だった。北京では、単色の制服が主流で、正統性と厳粛さはあるが、どこか活気に乏しかった。天津の人々は、細部に凝った仕立ての服をまとい、スタイルがあり、当時の北方三地域のなかでも、ファッション面で一歩先を行っているように感じられた。
私の稚拙な描写では、そこに宿っていた空気――物が帯びる「れ」のようなものを、どうにも伝えきれないのがもどかしい。自分の文章力を情けなく思う。そしてそれだけでなく、今日この目で北部工業地帯の衰退を見るたび、胸が締めつけられ、言葉が出なくなってしまうのだ。
3.
旧第一隊が担当していたのは、基本的に自噴油井――つまり水圧ポンプを必要としない自然噴出型の油井だった。ほとんどの井戸で、1万立方メートル以上の天然ガスが産出していたのを記憶している。
当時、すぐ近くの王徐庄油田では、何十本ものガストーチが燃え上がっていた。夜になると、それらの火柱が空を照らし、地面までがその光で赤く染まる。近くで見ると、金色の火の破片がパチパチと輝き、あまりの明るさに一時的に視界が白くなり、目の前に黒い影が浮かぶほどだった。遠目には、星が散りばめられたような幻想的な光景にも見えた。空に赤い火が揺らめき、夜空の半分をまるごと赤く染めていた。燃える音は、まるで猛獣の遠吠えのようで、胸がざわつくほどだった。
あの風景は、まるでおとぎ話の世界のようで、そうそう出会えるものではなかった。
油田では原油も天然ガスも豊富に産出されていたが、当時はまだガスの価値があまり認識されておらず、惜しげもなく燃やされていた。原油はまずタンクローリーで搬送され、その後はパイプラインで輸送されたが、天然ガスはその場でただ燃焼されるだけだった。
油田では原油も天然ガスも豊富に産出されていたが、当時はまだガスの価値があまり認識されておらず、惜しげもなく燃やされていた。原油はまずタンクローリーで搬送され、その後はパイプラインで輸送されたが、天然ガスはその場でただ燃焼されるだけだった。
だが、南大港農場の農民たちは、このガスの燃焼を見て考えはじめた。岐5号油井の南側、20メートルほどの地点には天然ガス乾燥機があり、南西側にはアドベハウスが並んでいた。岐639号油井の西側、堤防の外には、大きな車の修理屋があり、どこのチームが運営していたのか定かではないが、当時はかなり繁盛していた。
また、南大糖酒工場では天然ガスを活用し、PVCパイプを通じて供給していた。冬季の暖房としてはもちろんだが、主には酒の製造における発酵温度を一定に保つためだったのだろう。
南西3号のアドベハウスに住んでいた劉燕は、常にガス圧を確認していた。砂糖蒸留所への安定供給を確保するためである。南大港農場の蒸留所ではモロコシ酒を生産しており、その人気ぶりは供給が追いつかないほどだった。
「滄州の地酒を飲んでも黄驊に勝たん、黄河の地酒を飲んでも南大港に勝たん、南大港の地酒を飲んでも南鉱に勝たん」――
そんな韻を踏んだ言い回しが流行するほど、評判は高かった。
そんな韻を踏んだ言い回しが流行するほど、評判は高かった。
計画経済の時代には、原材料の生産も配給もすべて計画的に管理されていた。酒を買うにもチケットが必要で、入手は容易ではなかった。しかし南鉱の人々は人脈を駆使し、比較的スムーズに南鉱モロコシ酒を手に入れていた。
1本1元4厘。52度という高いアルコール度数にもかかわらず、「酔っても頭が痛くならない」「目が回らない」と評判で、品質は折り紙付きだった。
人が集まり、用意された酒を飲み干しても、誰かが「いや、まだ解散しないぞ」と言って、腰の後ろから南鉱モロコシ酒のボトルを取り出す。また少しして別の誰かが、さらにもう一本を差し出す。こうして宴は延々と続いていくのだった。
4.
余維海が月曜の例会で激昂した。会の最中、思いきって彼に反論する者が現れたのだが、意外にも、そのときの余維海は何も言い返せず、そのまま例会はあっけなく解散となった。
だが事態はその後、水面下でじわじわとエスカレートし、ついには波乱へと発展していく。私もその渦中に巻き込まれることになった。
最初に開かれたのは班長会議だった。夜遅くまで続けられ、任務が割り振られ、細かい指示が飛び交った。間を置かず、食堂や中庭のあちこちにいわゆる「大字報」が貼り出された。全員一致で、矛先は楊承剛に向けられた。文面の細部には若干の違いがあったものの、口調はどれもほぼ同じで、楊承剛を“泥棒”呼ばわりし、「千の拳で打て、万の足で踏め」と煽り立てる内容だった。
だが当の楊承剛には、まるで困っている様子が見えなかった。いつも通りに仕事をこなし、食べて、寝ていた。まるで綿の袖に鉄拳を打ち込むかのように、何の反応も返ってこない。ある日、余維海と楊承剛が宿舎のエリアですれ違い、互いに目を見開いて睨み合った場面を目撃したが、結局何も起こらなかった。
その後、1972年の総括会議が開かれた終盤に、旧チームリーダーの秦時棟が呼ばれて姿を見せた。
秦さんは、余維海が提出した報告書を最初の段階で受理した立場から、会議の席で楊承剛を叱責した。だが、具体的な証拠は何ひとつ提示されなかった。いくらチームリーダーの報告書といえど、それだけでは皆を納得させることはできなかった。
秦さんは、余維海が提出した報告書を最初の段階で受理した立場から、会議の席で楊承剛を叱責した。だが、具体的な証拠は何ひとつ提示されなかった。いくらチームリーダーの報告書といえど、それだけでは皆を納得させることはできなかった。
それでも秦さんは懸命に演説し、楊承剛を名指しし続けた。楊承剛は席に座ったまま、小さな声で応酬していた。その声は控えめだったが、出席者全員にはしっかりと届いていた。秦さんが名前を挙げるたびに、楊は目を伏せて呟き返す。会議の空気は次第に重苦しいものになっていった。秦さんの言葉も、まるで手応えを欠いていた。
すべての始まりは、11月末のことだった。そこから20日ほど経ち、総括会議が行われた。さらに10日もすれば、元日がやってくる。
「ここで尻すぼみに終わらせてはならない。沈黙は屈辱だ」――きっと、余維海はそう感じたに違いない。そして、私を呼び出した。
「ここで尻すぼみに終わらせてはならない。沈黙は屈辱だ」――きっと、余維海はそう感じたに違いない。そして、私を呼び出した。
あの余維海に、呼ばれる――。
いつも彼の前を通るだけで、心臓がバクバクするというのに。
いつも彼の前を通るだけで、心臓がバクバクするというのに。
彼はにこやかな顔を見せ、声を低くしてこう尋ねてきた。
「楊承剛の件、あなたはどう思う?」
「楊承剛の件、あなたはどう思う?」
私は思わず、大字報の文句そのままに答えていた。
「楊承剛のアナーキズムは深刻です。米のチケットを盗んだ泥棒です。」
「楊承剛のアナーキズムは深刻です。米のチケットを盗んだ泥棒です。」
「そうか。じゃあ、大字報を書いたのはあなたか?」
「はい、4枚。週に1枚ずつ書いています。」
「はい、4枚。週に1枚ずつ書いています。」
すると彼は、私を褒め、励ました。だが、その時私は、何かが間違っていると感じていた。
結局、余維海はさらに大字報を書けと私に言いつけた。
「あなたたちは北京から来た人だから、言葉づかいが違う。だからこそ、あなたの大字報にはインパクトがあるんだ!」
「あなたたちは北京から来た人だから、言葉づかいが違う。だからこそ、あなたの大字報にはインパクトがあるんだ!」
私は寮に戻り、彼の要望どおりに一枚書き上げた。
だが、その大字報は、掲示されることなく、ずっと貼り出されないまま残った。
だが、その大字報は、掲示されることなく、ずっと貼り出されないまま残った。
それから約1ヶ月が過ぎた春節前、孫福君がわざわざ私の寮を訪ねてきた。
今にして思えば、もしかしたら、彼はその「貼られなかった大字報」を見に来たのかもしれない――そんな気がしてならない。
今にして思えば、もしかしたら、彼はその「貼られなかった大字報」を見に来たのかもしれない――そんな気がしてならない。
5.
夏のある週末の夕暮れ、中庭に灯った水銀灯の下で、「大躍進」という名のカードゲームに興じていた。
すでに安定した職場に就いてはいたが、まだ独身で、どこか坊主頭の少年っぽさが抜けきらない男たちが集まり、夏用のズボンに裸の上半身という格好で、汗を光らせながらプレーしていた。6人がゲームに加わり、その周りをさらに何人かが取り囲んで観戦していた。
すでに安定した職場に就いてはいたが、まだ独身で、どこか坊主頭の少年っぽさが抜けきらない男たちが集まり、夏用のズボンに裸の上半身という格好で、汗を光らせながらプレーしていた。6人がゲームに加わり、その周りをさらに何人かが取り囲んで観戦していた。
張明吉はいつも身なりをきちんと整え、声を発する前に一瞬つっかえるような癖があり、興奮するとタイミングが遅れて、突然、大声で叫ぶことがあった。
彭秀仙は普段は口数が少ないのに、肩をむき出しにして、「カード見せろ!」と太い声を響かせていた。
倪春漢は、タバコを咥えながらさりげなくカードを切り出す。どこか計算高く、ずる賢いところがあって、天津人らしさがにじみ出ていた。彼らのゲームを眺めているだけでも、一種の娯楽だった。
彭秀仙は普段は口数が少ないのに、肩をむき出しにして、「カード見せろ!」と太い声を響かせていた。
倪春漢は、タバコを咥えながらさりげなくカードを切り出す。どこか計算高く、ずる賢いところがあって、天津人らしさがにじみ出ていた。彼らのゲームを眺めているだけでも、一種の娯楽だった。
トランプの“最も粋な遊び方”というのは、誰も無駄口を叩かず、黙々とカードを出し合い、ある瞬間に誰かが突然「ダブル3だ」と叫んで、ローテーブルにカードを「トン」と音を立てて投げる。そして、そこでゲームは一気に決着がつく。
かつては、負けた者の頬に細長い紙を貼りつけるという罰ゲームがあったのだが、時勢柄、それが別の“連想”を生んでしまうことから、現在はルールが変わり、負けた者は冷たい水を一気飲みすることになった。一気に飲み干したあとは、座らずに立ったまま次のゲームを続行する。そしてまた負けると、今度は水も飲めず、しゃがんだままゲームに参加するという罰が待っている。ずっとしゃがんでいると、腰やふくらはぎがジンジンと痛み出す。それでも誰もやめない。
勝っている者は、わざとカードをゆっくりと手に取り、悠然と考えているふりをしながら、負けている相手をじわじわと焦らせていく。
男子たちは、ほとんど女子と話すことがなかった。女子たちもまた、寮で同じようにトランプをしているのかどうか、誰も知らない。
ある人が「女子はトランプをやらない」と言っていた。編み物をして時間を潰しているらしい。
ある人が「女子はトランプをやらない」と言っていた。編み物をして時間を潰しているらしい。
中庭のゲームを立ち止まって見ていく女子は、ほとんどいなかった。
時折、戸惑ったようにちらっと一瞥をくれて、そのまま去っていく者はいたが、長く留まる者はいなかった。
時折、戸惑ったようにちらっと一瞥をくれて、そのまま去っていく者はいたが、長く留まる者はいなかった。
女子が中庭を通ると、男子たちは一団となって、無言で彼女に敬礼する。まるで中学生のようだった。
恥ずかしくなった女子が「ほら、やめなさいよ」と一言だけ残して足早に寮に戻ると、男子たちは声を上げてどっと笑った。
恥ずかしくなった女子が「ほら、やめなさいよ」と一言だけ残して足早に寮に戻ると、男子たちは声を上げてどっと笑った。
6.
天津産の「墨菊」というタバコは、地元ではちょっとした名物だった。
同じ等級には、河北産の「大境門」という銘柄もあったが、こちらは「墨菊」より1厘高い。そのふたつだけが、当時手に入る中では“良質”とされるタバコだった。
同じ等級には、河北産の「大境門」という銘柄もあったが、こちらは「墨菊」より1厘高い。そのふたつだけが、当時手に入る中では“良質”とされるタバコだった。
見習い期間を経て、正式な隊員として認められ、ランクが1から2に上がったとき、私の月給は33元から55元へと跳ね上がった。
その頃にはもう、まるで不良少年のように隠れてビクビクしながらタバコを吸う必要もなかった。
食事に困ることもなく、気持ちに余裕も出てきて、腹いっぱい食べ、好きなときにタバコを買って吸う――それは、いわば独身貴族の気楽さ、自立の証だった。
その頃にはもう、まるで不良少年のように隠れてビクビクしながらタバコを吸う必要もなかった。
食事に困ることもなく、気持ちに余裕も出てきて、腹いっぱい食べ、好きなときにタバコを買って吸う――それは、いわば独身貴族の気楽さ、自立の証だった。
喫煙者は誰しも「タバコはやめる、やめる」と言う。けれど、吸わない者のほうが、なぜかタバコを勧められる。
それが、スモーカーとしての第一段階だ。
一本勧められ、もらいタバコを続けているうちに、だんだんと自分でも買わないと気まずくなってくる。
すると、今度は自分でタバコを買うようになる。しかも、必ず“良質な”やつを買う。
そして、人が集まれば真っ先にタバコを差し出すようになる。これが第二段階だ。
それが、スモーカーとしての第一段階だ。
一本勧められ、もらいタバコを続けているうちに、だんだんと自分でも買わないと気まずくなってくる。
すると、今度は自分でタバコを買うようになる。しかも、必ず“良質な”やつを買う。
そして、人が集まれば真っ先にタバコを差し出すようになる。これが第二段階だ。
一箱のタバコは、最初のうちは一週間、あるいは十日ほどで吸いきる。
「吸っても吸わなくても、別にどうでもいい」と思っていたが、
いつの間にか、一人の時間にも手が自然に伸びるようになる。
「吸っても吸わなくても、別にどうでもいい」と思っていたが、
いつの間にか、一人の時間にも手が自然に伸びるようになる。
そこから、咳や痰が出始める。
体の変化を感じ、「そろそろやめようかな」と思うようになる。
この時期が、喫煙人生の中で最もやめやすく、同時に最もやめにくい段階とも言える。
体の変化を感じ、「そろそろやめようかな」と思うようになる。
この時期が、喫煙人生の中で最もやめやすく、同時に最もやめにくい段階とも言える。
やめやすい理由は、まだ中毒レベルには達しておらず、やめたからといって身体に大きな異変は起きないからだ。
10日間でも2週間でも、あるいは数ヶ月でも、禁煙していられる。
問題は、その間に周囲のヘビースモーカーたちからの“誘惑”が襲ってくることだ。
10日間でも2週間でも、あるいは数ヶ月でも、禁煙していられる。
問題は、その間に周囲のヘビースモーカーたちからの“誘惑”が襲ってくることだ。
「一本だけ、どうだ?」――
それで一本吸ってしまえば、またタバコを買うようになり、しかもまた“良いやつ”を選ぶ。
その頃にはすっかり第二段階に逆戻りし、知らぬ間にニコチンの虜となっている。
それで一本吸ってしまえば、またタバコを買うようになり、しかもまた“良いやつ”を選ぶ。
その頃にはすっかり第二段階に逆戻りし、知らぬ間にニコチンの虜となっている。
そしてまた「やめる」と言いつつ、本数がどんどん増えていることに気づくのは、だいぶ後になってからだ。
断続的にやめたり吸ったりを繰り返しているうちに、10日に1箱が1週間に1箱となり、さらに2日に1箱、最後には1日1箱が当たり前になる。
断続的にやめたり吸ったりを繰り返しているうちに、10日に1箱が1週間に1箱となり、さらに2日に1箱、最後には1日1箱が当たり前になる。
タバコは、静かに、確実に、自分の時間を、呼吸を、日常を蝕んでいく。
王和群は「老一队」にいたことがないのだが、私はずっとどこかに違和感を抱いていた。張慎民が「老三队」から人を率いて南下したとき、王和群はいなかったのか?そうでなければ、南矿や二队・三队ができた後に、港東から調整されたのかもしれない。ちなみに「老三队」は「马西采油队」、のちに「采油指挥部」となり、さらに「采油一矿」から分かれて「采油四矿一队」へと再編された。
「老一队」には共働きの家庭もいた。たとえば張新华と封新焕。
彼ら二人は隊で公開批判を受けたことがある。封新焕は女性で、背も高くはなかったが、その批判には全く怯む様子がなかった。当時、名前を挙げられて批判を受けるというのは非常に重大なことで、誰しも足が震えるような場面だった。しかし封新焕は、一人の若い女性でありながら、まったく怖がらず、頑として譲らない態度を崩さなかった。あれは本当に見事だった。
彼ら二人は隊で公開批判を受けたことがある。封新焕は女性で、背も高くはなかったが、その批判には全く怯む様子がなかった。当時、名前を挙げられて批判を受けるというのは非常に重大なことで、誰しも足が震えるような場面だった。しかし封新焕は、一人の若い女性でありながら、まったく怖がらず、頑として譲らない態度を崩さなかった。あれは本当に見事だった。
「大批判」と言えば、私たちが「老一队」に着任して最初に大批判を受けたのは孫海大哥だった。
私が言う「大批判」とは、いくつかの要素を満たす必要がある。第一に、本人が大会で自己批判を行うこと。第二に、隊や班から指名された人物が批判発言をすること。そして第三に、批判会が一度ではなく複数回行われることである。批判会には、隊単位・班組単位・さらには鉱区全体での開催が含まれる。
私が言う「大批判」とは、いくつかの要素を満たす必要がある。第一に、本人が大会で自己批判を行うこと。第二に、隊や班から指名された人物が批判発言をすること。そして第三に、批判会が一度ではなく複数回行われることである。批判会には、隊単位・班組単位・さらには鉱区全体での開催が含まれる。
この三要素をすべて満たしていたのは、まず孫海、次に陳長発・張淑珍、そして楊成剛、さらに左清波・劉樹義。五番目が張新华と封新焕であった。
なお、孔子(孔丘)は除く。彼は2000年以上前の人物で、「老一队」のメンバーではないからだ。
なお、孔子(孔丘)は除く。彼は2000年以上前の人物で、「老一队」のメンバーではないからだ。
いま振り返っても、なぜ孫海が「無政府主義の黒幕」として批判されたのか、よくわからない。
“黒幕”を摘発するならば、“前台”の無政府主義者も現れるはずなのに、一人も出てこなかった。
私たちが「老一队」に着いたころ、ちょうど「南一注水站」が建設を終えたばかりだった。
油建が建設を進める中で、注水站の職員の一部はすでに現場入りしていた。しかし当初は仕事も少なく、勤務はかなり緩慢だったように記憶している。
“黒幕”を摘発するならば、“前台”の無政府主義者も現れるはずなのに、一人も出てこなかった。
私たちが「老一队」に着いたころ、ちょうど「南一注水站」が建設を終えたばかりだった。
油建が建設を進める中で、注水站の職員の一部はすでに現場入りしていた。しかし当初は仕事も少なく、勤務はかなり緩慢だったように記憶している。
孫海大哥は河北・唐山の出身で、「工读生」の世代だったと思う。
冗談好きで、時に突拍子もないことを言う癖があった。それが災いしたのか、まさかの批判対象となってしまった。
――“鶏を殺して猴を戒める”のか、“猴を殺して鶏を驚かす”のか?どちらも違う気がする。
冗談好きで、時に突拍子もないことを言う癖があった。それが災いしたのか、まさかの批判対象となってしまった。
――“鶏を殺して猴を戒める”のか、“猴を殺して鶏を驚かす”のか?どちらも違う気がする。
当時の注水站の人員構成は次のようだった:
站長の鄭元三と副站長の占万福は、どちらも「大慶入関」出身。
張玉良、張樹鵬(建設団)、孫海が「工读生」組。
郭恩秋、徐慶義、斉学智が西郊から。
そして、崔雨、彭樹森、倪春漢、張明吉は天津の70・71届出身。
站長の鄭元三と副站長の占万福は、どちらも「大慶入関」出身。
張玉良、張樹鵬(建設団)、孫海が「工读生」組。
郭恩秋、徐慶義、斉学智が西郊から。
そして、崔雨、彭樹森、倪春漢、張明吉は天津の70・71届出身。
注水站が稼働直前である以上、站長ふたりを批判することは現実的ではなかった。
西郊組は比較的おとなしく、標的にされにくい。
消去法でいえば、天津出身者たちが最も“挨整”されやすかったわけだ。
西郊組は比較的おとなしく、標的にされにくい。
消去法でいえば、天津出身者たちが最も“挨整”されやすかったわけだ。
盛茂民は後に「羊三木」から「老一队」へ副隊長として異動してきた。
彼は背が高く、濃い眉に鋭い目つき。肌が白く、容貌も整っていて、バスケットボールが得意だった。
とくにレイアップの動きにはキレがあり、中・遠距離のジャンプシュートもかなり正確だった。
彼は背が高く、濃い眉に鋭い目つき。肌が白く、容貌も整っていて、バスケットボールが得意だった。
とくにレイアップの動きにはキレがあり、中・遠距離のジャンプシュートもかなり正確だった。
鉱機関のバスケットチームといえば、羅志斌のほか、修理隊の李国桩・李国棟兄弟、試井班の小史もいた。小史は私たちより年上だったが、正確な名前は思い出せない。
また、裁判役の蘇顯玉や徐福貴も、プレイヤーとしてもなかなかの腕前だった。
また、裁判役の蘇顯玉や徐福貴も、プレイヤーとしてもなかなかの腕前だった。
孔憲華(二哥)は、海軍から転業してきた人物で、天津東郊の「軍糧城」の出身。
私たちが一队に来たときにはすでに結婚していた。
聞いた話だが、彼の新婚初夜、誰かのいたずらで布団に“矿渣棉”が仕込まれていたらしい。
夜中に二哥と嫂子がかゆみで目を覚まし、布団を解いて洗うはめになった。ちょっと悪ノリが過ぎた。
私たちが一队に来たときにはすでに結婚していた。
聞いた話だが、彼の新婚初夜、誰かのいたずらで布団に“矿渣棉”が仕込まれていたらしい。
夜中に二哥と嫂子がかゆみで目を覚まし、布団を解いて洗うはめになった。ちょっと悪ノリが過ぎた。
彼は胃が弱く、ずっと痩せていた。だが、その「蹲功」は他の追随を許さなかった。
地面にしゃがんでも、尻がかかとにぴったりつき、1時間続けても足が痺れない。
地面にしゃがんでも、尻がかかとにぴったりつき、1時間続けても足が痺れない。
1981年の元旦、私は沈老師と知り合い、彼女の実家である「軍糧城」を訪ねた。
その道中、孔二哥の家の前を通りかかると、沈先生が「あれが孔憲華さんの家ですよ」と教えてくれた。
のちに本人に会ったとき、「こないだ軍糧城行ったよ」と言ってみたが、彼は「信じない」と笑って取り合わなかった。
そこで私は軽く冗談を飛ばした。
その道中、孔二哥の家の前を通りかかると、沈先生が「あれが孔憲華さんの家ですよ」と教えてくれた。
のちに本人に会ったとき、「こないだ軍糧城行ったよ」と言ってみたが、彼は「信じない」と笑って取り合わなかった。
そこで私は軽く冗談を飛ばした。
「おたくの庭の塀って、あれ、プレス鉄片の端材で編んだフェンスでしょ?」
「それから、お宅の北東には微生物工場と小さな病院があるでしょ?」
「それから、お宅の北東には微生物工場と小さな病院があるでしょ?」
全部当たっていたので、二哥はびっくりして「なんでそんなこと知ってるんだ」と食いついてきた。
でも私は、最後まで何をしに行ったかは言わなかった。
でも私は、最後まで何をしに行ったかは言わなかった。